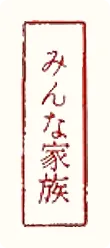子ども支援の現場で信頼形成を実現する企画と実践アプローチ
2025/10/22
子ども支援の現場で、信頼形成に悩んだことはありませんか?日々接する子どもたち一人ひとりの心に寄り添いながら、その個性や感情を理解し、安心できる関係を築くことは簡単なようで奥深い課題です。背景には、自己肯定感や成長段階に応じた適切な関わり方、そして保護者との連携など多様な視点が求められ、現場ではさまざまな工夫が試みられています。本記事では、企画と実践を通じて信頼形成を促進する効果的なアプローチを具体例とともに紹介します。子ども支援の学びを深め、子どもの自信や笑顔を引き出すためのヒントが得られる内容です。
目次
子ども支援に信頼を築く企画力とは

子ども支援企画が信頼形成に果たす役割を解説
子ども支援企画は、子どもと大人との信頼関係を築くための重要な基盤となります。信頼形成がなければ、子どもたちは自分の気持ちや考えを安心して表現することが難しくなり、支援の効果も十分に発揮されません。企画を通じて子ども同士やスタッフとの交流機会を設けることで、自然な関わりや対話が生まれ、信頼関係が育まれていきます。
たとえば、ワークショップやイベントを定期的に開催し、子どもが「やってみたい」と思える活動を取り入れることで、自発的な参加と達成感を引き出すことが可能です。こうした経験の積み重ねが「自分は受け入れられている」という安心感につながり、信頼形成の土台となります。支援企画は単なる楽しみの場ではなく、子どもの成長や自己肯定感を高めるための大切な仕組みです。

信頼関係構築に必要な子ども支援の視点と工夫
信頼関係構築には、子どもの視点に立って関わる姿勢が不可欠です。大人の都合や価値観を押し付けるのではなく、子ども一人ひとりの気持ちや発達段階を理解し、丁寧に寄り添うことが大切です。たとえば、子どもの話を最後まで聞く・否定しない・共感の言葉をかけるなど、日常の小さな積み重ねが信頼につながります。
また、子どもが失敗したときや不安を感じたときに、安心して相談できる環境をつくる工夫も重要です。具体的には「どんな気持ちだった?」と感情に寄り添い、子どものペースで話せる時間を確保することが効果的です。子ども支援では、こうした日々の工夫が信頼関係の強化に直結します。

子ども支援で求められる信頼形成の基本要素
子ども支援における信頼形成の基本要素は「一貫性」「共感」「安心感」「尊重」の4つです。まず、一貫性のある対応は子どもにとって予測可能な環境をつくり、不安を和らげます。次に、共感的な関わりは、子どもの感情や経験を受け止める姿勢として不可欠です。
さらに、安心感のある空間を提供し、子どもが自分らしくいられる環境を整えること、そして子どもの意見や意思を尊重することが信頼形成には欠かせません。これらの要素をバランスよく実践することで、子どもは「自分は大切にされている」と感じ、信頼関係が深まります。現場ではスタッフ同士の連携も大切にし、子どもがどの大人にも安心して接することができるよう配慮が必要です。
安心感を生む子ども支援の関わり実例

安心感を高める子ども支援企画の実践例と効果
子ども支援の現場で安心感を高めるためには、日常的な企画やイベントを通じて、子どもたちの「やってみたい」「話してみたい」という気持ちを引き出すことが重要です。たとえば、自由な発想を大切にした遊びや、興味関心に応じた体験型のワークショップは、子どもが自分らしさを発揮できる環境をつくります。
こうした企画は、子どもが大人に心を開きやすくなるだけでなく、安心して失敗や挑戦を経験できる場にもなります。信頼関係が深まることで、自己肯定感や社会性の発達も促される点が大きな効果です。保育や子ども支援の専門家によると、安心できる環境があることで、子どもは感情を安定させ、成長段階に応じた適切な行動をとれるようになると言われています。
実際の現場では、スタッフが子どもの目線に立ち、小さな変化や要望にも丁寧に応える姿勢が、信頼形成の基盤となっています。例えば、ある支援現場では「みんなのアイデアを実現する日」と称して、子どもたち自身が企画の主役となる活動を実施し、大きな笑顔と自信につながったという声が寄せられています。

子ども支援で信頼を深める関わり方のポイント
子どもとの信頼関係を築くためには、まず「子どもの気持ちを受け止める」姿勢が不可欠です。一方的な指導や評価ではなく、子どもの言葉や行動の背景にある感情や意図を理解しようとする関わりが求められます。
具体的には、子どもが話す内容を否定せずに聴き、共感を示すことが大切です。また、約束を守る、失敗を責めずに次の挑戦を応援するなど、日々の積み重ねが信頼の土台となります。保育や支援の現場では「NGワード」を避け、子どもの自尊心を傷つけない配慮も重要です。
たとえば、「どうせできないでしょ」といった否定的な言葉は避け、子どもの努力や工夫を認める声かけを心がけましょう。こうした積極的な関わりが、子どもが大人を信頼し、自分の気持ちを安心して伝えられる環境づくりにつながります。

子ども支援で安心を生むコミュニケーション術
子ども支援の現場では、安心感を生むコミュニケーションが信頼形成に直結します。子どもが話しやすい雰囲気をつくるためには、アイコンタクトやうなずき、適度な沈黙も活用しながら、子どものペースを尊重することが大切です。
また、子どもが言葉にできない気持ちを表現できるよう、絵や遊びを取り入れた非言語的なコミュニケーションも効果的です。たとえば、自由画やごっこ遊びを通じて子どもの思いや悩みを汲み取ることができ、子ども自身も「わかってもらえた」という安心感を得られます。
現場では、子どもの発言や行動を否定せず、肯定的に受け止めることが信頼形成のポイントです。こうしたコミュニケーションを意識的に積み重ねることで、子どもは大人との距離を縮め、安心して支援を受け入れやすくなります。

発達段階に合わせた子ども支援の信頼形成実践
子どもは年齢や発達段階によって必要とする関わり方や安心の感じ方が異なります。例えば、乳幼児期にはスキンシップや一貫した対応が「愛着形成」に不可欠であり、学童期には自立を促す声かけや成功体験の積み重ねが信頼形成に役立ちます。
発達段階ごとに「子供の発達段階表」や「愛着形成チェックリスト」などを参考にしながら、個々の子どもの状態に合わせた支援を行うことが大切です。特に思春期には、自己主張と葛藤が増えるため、否定せずに見守る姿勢や、プライバシーへの配慮が信頼関係維持のポイントとなります。
実際の現場では、発達段階に応じた対応を意識することで「気持ちが分かってもらえた」と感じる子どもが増え、行動や感情の安定につながったという声が多く寄せられています。年齢や成長に合わせた柔軟な関わりが、信頼形成の基盤となります。

保護者と協力する子ども支援の信頼構築方法
子ども支援の現場で信頼関係を築くためには、保護者との連携が欠かせません。保護者と情報共有を密に行い、子どもの家庭での様子や成長に関する意見を尊重することが重要です。
具体的には、定期的な面談や連絡ノートを活用し、子どもの小さな変化や気になる点を共有することが効果的です。また、保護者が不安や疑問を持った際には、迅速かつ丁寧に対応することで、相互の信頼が深まります。保護者との協力体制を築くことで、子どもにとってより安心できる支援環境が整います。
現場では「保護者と支援者が一体となって子どもの成長を見守る」という姿勢が、子どもの安心感や自信につながったという声も多く聞かれます。保護者との関係を大切にしながら、子ども支援を進めることが信頼形成の大きなポイントです。
信頼形成に役立つ企画の工夫と発想法

信頼形成に効く子ども支援企画のアイデア集
子ども支援の現場では、信頼形成を目的とした企画が重要です。信頼関係を築くためには、子ども一人ひとりの気持ちや発達段階を理解し、安心できる環境を整えることが求められます。例えば、日常的な遊びや話し合いの時間を設けることで、子どもたちが自分の思いを自然と表現できるようになります。
具体的なアイデアとしては、グループワークや体験型イベント、自己紹介ゲーム、感情カードを使ったコミュニケーションの促進などが挙げられます。こうした活動を通じて子ども同士やスタッフとの関わりが深まり、信頼の基盤が築かれていきます。保護者との連携を図る企画も有効で、家庭と支援現場が一体となって子どもを支える体制づくりが信頼形成に直結します。
実際の現場では、子どもから「また来たい」と言われるような、安心感と楽しさを両立したイベントが好評です。これらの企画は、子どもたちの自己肯定感や社会性の発達にも大きく寄与します。

子ども支援現場の信頼構築に必要な工夫とは
信頼構築には、日々の小さなやり取りの積み重ねが不可欠です。子どもの発達や感情に寄り添い、共感的な対応を心がけることで、安心できる関係性が生まれます。特に、子どもの話を否定せずに受け止める姿勢や、目線を合わせて関わることが大切です。
また、愛着形成の観点からも、安定した大人との関わりは子どもの情緒の安定に直結します。例えば、決まった時間に同じスタッフが対応する、笑顔での挨拶や名前を呼ぶなど、日常のルーティンを意識することが効果的です。
さらに、子どもが自分で選択できる場面を増やすことで「自分を大切にされている」という実感が生まれ、信頼関係が深まります。失敗や不安を感じたときも、温かくサポートする姿勢を持ち続けることが重要です。

子ども支援で役立つ信頼形成の発想法を解説
信頼形成のための発想法として、まず「子どもの立場に立つ」ことが挙げられます。子どもが何を感じ、どんなことに関心を持っているかを想像し、その気持ちに共感することが基本です。発達段階や個人差を意識しながら、柔軟にアプローチを変える発想が求められます。
例えば、言葉選びや態度に配慮することで、子どもの安心感や自己肯定感を高めることができます。具体的には、否定的な言葉や強い命令口調を避け、できたことや努力を認める声かけを意識しましょう。
また、子ども自身が「信頼されている」と感じられるような役割やチャレンジの機会を設けることも効果的です。実際の現場では、子どもが意見を出し合ってイベント内容を決めたり、小さなリーダー役を体験することで自信と信頼が育まれています。

発達段階を意識した子ども支援企画の工夫例
子どもの発達段階に応じた支援企画を設計することは、信頼形成において非常に重要です。幼児期には遊びや身体表現を中心に、学童期にはグループ活動やルールを取り入れた企画が適しています。発達段階ごとの特性を理解し、子どもが無理なく参加できる内容を考えることがポイントです。
例えば、幼児にはお絵かきやリズム遊び、小学生には協力ゲームや話し合い活動を用意することで、それぞれの成長に合った体験を提供できます。こうした工夫は、子どもが「分かってもらえている」と感じるきっかけとなり、信頼関係の強化につながります。
また、発達段階を意識した関わりは、愛着形成や社会性の発達にも良い影響を与えます。年齢や個性に合わせた柔軟な対応を心がけることで、子どもが安心して自分を表現できる環境が整います。

子ども支援で信頼を高める実践的な企画設計
実践的な企画設計では、子ども主体の活動を重視することが信頼形成の鍵となります。子どもが自分の意見や希望を伝えやすい仕組みを作り、スタッフがその声を丁寧に受け止めることが大切です。例えば、活動前に子どもたちと一緒に目標を決めたり、活動後に感想を共有する時間を設けるといった工夫があります。
また、子ども同士が協力し合う場面を増やすことで、集団内での信頼関係も育まれます。スタッフは子どもの気持ちの変化に敏感に気づき、適切なサポートを行うことが求められます。失敗やトラブルがあった際も、頭ごなしに指摘するのではなく、どうすればよかったのか一緒に考える姿勢が信頼を深めます。
このような実践を積み重ねることで、子どもが自分自身や他者を信じる力を育み、豊かな人間関係を築く土台となります。現場での工夫や成功事例を参考にしながら、より良い支援企画を目指しましょう。
愛着形成を促す子ども支援の進め方

愛着形成を意識した子ども支援企画の手法紹介
子ども支援の現場で信頼関係を育むためには、「愛着形成」を意識した企画が欠かせません。愛着とは、子どもが安心して頼れる大人との間に築く心の絆を指し、健やかな成長や自己肯定感の基盤となります。現場では、子ども一人ひとりの気持ちや発達段階を理解し、それに応じた支援プランを立てることが重要です。
具体的な手法としては、日常的なやり取りや遊びを通じて子どもの興味や感情に寄り添い、主体的な参加を促す活動を企画します。また、信頼できる大人が一貫性のある対応や共感的な言葉がけを心がけることで、子どもは安心感を覚えやすくなります。
例えば、グループワークや体験型イベントでは、子ども自らが意見を出し合い、他者と協力するプロセスを大切にします。こうした体験を重ねることで、子どもが「自分を大切にしてくれる大人がいる」と感じ、信頼形成につながります。

子ども支援で信頼と愛着を育てる実践ポイント
子ども支援の現場で信頼と愛着を育てるためには、まず子どもの話に丁寧に耳を傾ける姿勢が大切です。大人が子どもの目線に立ち、肯定的な言葉や態度で接することで、子どもは安心して自分の気持ちを表現できるようになります。
また、日々の小さな約束を守ることや、失敗したときも温かく受け止めることが信頼関係の基盤となります。例えば「できて当たり前」と考えず、努力や挑戦そのものを認める言葉を意識的にかけることが重要です。
さらに、保護者や他の支援者と情報共有を行い、支援方針を統一することで子どもに一貫した安心感を与えます。これにより、子どもはさまざまな場面で自分を受け止めてくれる大人の存在を実感できます。

子ども支援現場で活きる愛着形成の関わり方
子ども支援現場では、愛着形成を意識した関わり方が信頼関係の構築に直結します。まず、子どもが困っているときや不安を感じているときには、すぐに対応できる距離感を保つことが大切です。子どものサインに気づき、寄り添う姿勢を見せることで「自分は大切にされている」と感じやすくなります。
また、子どもが自発的に行動できるよう見守り、必要に応じてサポートすることも効果的です。過度な干渉を避け、子どものペースや意欲を尊重することで、自己肯定感と信頼感が高まります。
実際の現場では、個別面談や日誌の活用を通じて子どもの気持ちや行動を把握し、関わり方を調整する工夫が求められます。特に保育や教育の場では、子どもの発達段階や家庭環境を考慮した柔軟な対応が信頼形成の鍵となります。

発達段階に応じた愛着形成支援の企画例
子どもの発達段階に応じた愛着形成支援は、効果的な企画を立てるうえで不可欠です。例えば、乳幼児期にはスキンシップや一対一のふれあいを重視した遊びを取り入れ、安定した情緒の発達を促します。幼児期以降は、友達や集団との関わりを楽しめるグループ活動が有効です。
発達段階ごとに適した支援内容を考えることで、子どもが自分に合った形で大人との信頼関係を築くことができます。例えば、学校との連携を強化し、専門職によるカウンセリングやメンタルサポート体制を整えることで、子どもの不安や悩みに早期対応が可能となります。
また、保護者と連携しながら家庭と支援現場をつなぐサポートも重要です。子どもの「今」の状態を正しく把握し、成長を見守る姿勢が愛着形成と信頼の深化につながります。

愛着形成チェックを活用した子ども支援の工夫
愛着形成の状況を定期的にチェックすることは、子ども支援の質を高めるうえで有効な工夫です。「愛着形成チェックシート」などのツールを活用し、子どもの行動や感情の変化を客観的に把握します。これにより、支援者が早期に課題を発見し、適切な対応策を講じることができます。
チェック結果をもとに、個別支援計画を見直したり、保護者や関係機関と連携して支援内容を調整することが可能です。例えば、子どもが不安や緊張を感じている場合は、安心感を与える関わり方や環境調整を行います。
愛着形成チェックを定期的に行うことで、子ども一人ひとりの成長や変化にきめ細かく対応でき、信頼関係のさらなる深化が期待できます。支援現場では、こうしたチェックを通じて子どもの「今」を理解し、より良い支援を実現しましょう。
成長段階に応じた支援企画と信頼関係

発達段階別の子ども支援企画で信頼を築く方法
子ども支援の現場では、発達段階ごとに異なるアプローチが求められます。信頼形成を目指すためには、子どもの年齢や発達に応じた企画を立てることが重要です。たとえば、幼児期には遊びや日常のやり取りを通じて安心感を与えること、小学生期にはグループ活動や自己表現の機会を設けることが効果的です。
こうした実践を行う際には、子ども一人ひとりの気持ちや反応に丁寧に寄り添うことが信頼関係の構築につながります。例えば、日々の活動の中で「できたね」「がんばったね」といった肯定的な言葉をかけることで、自己肯定感を育みやすくなります。また、子どもが困ったときや悩んだときには、すぐに相談できる環境を整えることもポイントです。
発達段階別の支援企画を考える際は、愛着形成やアタッチメントの理論も参考になります。子どもの成長や感情の安定を支える基盤として、日常的な関わりや信頼できる大人の存在が不可欠です。現場では、子どもたちの小さな変化やサインを見逃さず、柔軟に対応することを心がけましょう。

子どもの成長段階に合わせた信頼形成アプローチ
子どもの成長段階に合わせた信頼形成のアプローチは、安心できる関係性の基盤となります。特に幼少期は、保護者や支援者が子どもの感情やニーズに敏感に反応し、愛着形成を促すことが大切です。保育園や学校現場でも、普段のやり取りを通じて子どもの気持ちに寄り添う姿勢が求められます。
具体的には、子どもの行動や言葉を否定せずに受け止める、日々の小さな成功体験を一緒に喜ぶ、困難な場面では「大丈夫だよ」と安心感を与えるなどの声かけが有効です。また、信頼関係を損なうNGワードを避けることも重要です。例えば「どうせできない」や「もう知らない」といった否定的な言葉は、子どもの自己肯定感を傷つけてしまうため注意が必要です。
成長段階ごとに適切な関わり方を意識しながら、子どもが安心して自分を表現できる環境を整えることで、信頼形成がスムーズに進みます。現場では保護者や他の支援者とも連携し、子どもを中心にしたチーム支援体制を構築することが成功の鍵です。

信頼構築に役立つ発達段階対応子ども支援企画
信頼構築に役立つ子ども支援企画として、発達段階に応じた体験や活動を取り入れることが効果的です。たとえば、幼児期には安心できる遊びやスキンシップを中心に、小学生期には挑戦できるプロジェクトやグループワークを通じて達成感を味わえる機会を提供します。
こうした企画を進める際には、子どもたちの意見や気持ちを尊重し、主体的な参加を促すことが信頼関係の深化につながります。実際に、イベントの企画段階から「どんなことをしたいか」を子どもに尋ね、アイデアを反映させることで、「自分の思いが大切にされている」と感じられるようになります。
また、失敗やトラブルが起きた際も一緒に解決策を考えることが重要です。大人が一方的に決めるのではなく、子どもの視点に立って共に行動することで、子どもは安心感と信頼を深めていきます。こうした積み重ねが、長期的な信頼関係の土台となります。

子ども支援で注目したい成長段階と関わり方
子ども支援の現場では、成長段階ごとに適した関わり方を意識することが大切です。愛着形成やアタッチメントの時期には、安定した大人との関係が子どもの情緒や社会性に大きな影響を与えます。特に保育園や家庭での関わりは、その後の人間関係の基盤となるため、丁寧な対応が求められます。
具体的には、子どもの発達段階を「愛着形成期」「自立期」「社会性発達期」などに分け、それぞれに応じた声かけやサポート方法を考えましょう。たとえば、愛着形成期にはスキンシップやアイコンタクトを多く取り入れ、自立期には挑戦を見守り、必要に応じてサポートする姿勢が有効です。
また、子どもが安心して自分を表現できるよう、否定的な言葉を避け、肯定的なコミュニケーションを心がけます。現場での実践例として、困っている子どもに「どうしたの?」と声をかけることで、安心感を与え信頼関係を深めることができます。

子ども支援企画で成長を支える信頼の築き方
子ども支援企画を通じて成長を支えるためには、信頼の築き方に工夫が必要です。まず、子ども一人ひとりの個性や感情を理解し、日々のやり取りを重ねることが大切です。小さな変化やサインに気づき、適切に対応することで、子どもは「見てもらえている」と感じ、安心して行動できます。
また、子どもが自分の思いを自由に表現できる機会を設けることも信頼形成には欠かせません。例えば、グループ活動やイベントで子どものアイデアを採用し、実際に形にすることで「自分の声が反映される」経験を積むことができます。こうした積極的な関わりは、自己肯定感や社会性の発達を後押しします。
さらに、保護者や地域との連携も信頼形成には重要な要素です。支援者だけでなく、周囲の大人たちが協力し合うことで、子どもにとってより安心できる環境が整い、長期的な成長を支える基盤となります。
保育現場で生きる信頼づくりのアイデア

保育現場に活かせる子ども支援企画の信頼術
保育現場で子ども支援を行う際、信頼形成の基盤となるのは「子ども一人ひとりの気持ちや発達段階を理解し、安心できる環境を整えること」です。特に愛着形成の時期には、子どもが自分の感情を安心して表現できるような関わり方が重要になります。信頼を築くためには、日常の小さなやりとりを大切にし、子どもが困ったときや嬉しいときに寄り添う姿勢が求められます。
具体的な企画例としては、子どもたち自身がやってみたい活動を聞き取り、イベントや遊びの内容に反映することが挙げられます。例えば「みんなでお店屋さんごっこをしたい」といった声を取り入れることで、子どもたちの主体性と信頼感が高まります。また、ボランティアや地域の大人も巻き込むことで、子どもが多様な大人と関われる安心した環境づくりが可能となります。
こうした企画を進める上での注意点は、子どもの思いを否定せず、保育者が先回りして決めすぎないことです。子どもが自分で考え、選択できる余地を残すことで、信頼関係がより深まります。

子ども支援で信頼を築く保育者の取組事例集
信頼される保育者になるためには、子ども一人ひとりの個性や発達段階に合わせた対応が不可欠です。たとえば、ある保育園では「朝の挨拶を必ず目を見て行う」「子どもの話を最後まで丁寧に聞く」といった基本的なコミュニケーションを徹底しています。これにより、子どもは自分が受け入れられていると感じ、安心して気持ちを表現できるようになります。
また、失敗したときやトラブルが起きたときも頭ごなしに叱るのではなく、「どうしたかったのか」「どんな気持ちだったのか」を聞き出す姿勢が信頼関係の構築につながります。例えば、「お友だちとけんかしたけど仲直りできた」という事例では、保育者が間に入り、双方の気持ちを言葉にして整理することで、子ども同士の信頼も深まります。
取組の際には、愛着形成のチェックや子どもの発達段階表を活用し、個々の子どもに合った支援策を検討することが効果的です。

保育の現場で役立つ信頼形成の声かけと工夫
子ども支援で信頼関係を築くためには、日々の声かけや言葉選びが大きな役割を果たします。たとえば、「できるよ、やってみよう」「困ったらいつでも相談してね」といった前向きな言葉は、子どもの自己肯定感を高め、安心感を与えます。一方で、「どうしてそんなことしたの?」など否定的なNGワードは避け、子どもの気持ちを受け止める姿勢が大切です。
信頼形成のための工夫としては、子どもの発言や行動をすぐに評価せず、「そう思ったんだね」「頑張ったね」と気持ちに共感することがポイントです。また、日々の活動の中で「一緒にやろう」「ありがとう」といった感謝や協力を伝えることで、子どもとの距離が縮まります。
実際の現場では、子どもが不安になったときや新しいことに挑戦する際に、保育者がそっと寄り添い、安心できる言葉をかけることで、信頼関係がより強固なものとなります。

子ども支援の現場で生まれる信頼関係の実際
子ども支援の現場では、信頼関係が育まれる瞬間が日常的に見られます。たとえば、子どもが「先生、今日こんなことがあったよ」と自ら話しかけてくれる場面は、信頼が築かれている証拠です。また、新しい活動に不安を感じている子どもが、保育者のサポートで一歩踏み出せたとき、その経験が信頼の積み重ねとなります。
一方で、信頼関係がうまく築けていない場合には、子どもが本音を言えなかったり、指示に従わない行動が増えることもあります。こうしたときは、再度子どもの気持ちや環境を見直し、安心できる関わりを心がけることが大切です。
実際の現場では、子どもの自己肯定感や愛着形成の段階を見極めながら、適切な関わり方を工夫し続けることが信頼関係の維持・発展につながります。

保護者と連携する子ども支援の信頼構築方法
子ども支援においては、保護者との連携も信頼形成の重要な要素です。保護者との情報共有や日々のコミュニケーションを丁寧に行うことで、子どもの成長や発達について共通理解を持つことができます。例えば、連絡帳や面談を活用し、子どもの様子や変化を具体的に伝えることが信頼関係の基盤となります。
また、保護者からの相談や要望には真摯に耳を傾け、必要に応じて専門機関と連携する姿勢も大切です。例えば、子どもの発達や行動について不安がある場合には、速やかに関係機関と連携し、最適な支援につなげることが信頼構築につながります。
注意点としては、保護者の気持ちや家庭環境にも配慮しつつ、子どもの最善の利益を第一に考えて支援を進めることが求められます。